代理権の範囲について定めがない場合には、代理権の範囲は「保存行為」と「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」に限られます。「保存行為」だけではありません。
「代理」知識まとめ
| ✅ 正しい理解 | ❌ 間違えやすいポイント |
|---|---|
| 代理とは「他人の名で法律行為をすること」。その効果は本人に帰属する。 | 「代理人自身の契約」になると誤解しがち。実際は本人に帰属する。 |
| 無権代理(権限のない代理)は原則無効。ただし、本人が追認すれば有効になる。 | 「無権代理でも相手がOKなら有効」と誤解しがち。➡️本人の追認が必要 |
| 相手方が、無権代理であることを知らなかった場合でも原則無効 | 「善意なら保護される」と誤解しがち。➡️保護されない(民法改正後も基本同じ) |
| 代理権の範囲を超えた行為(例:売却代理で抵当権設定)は無権代理になる | 「似た行為ならOK」と思いがち。でも、超えたらNG |
| 権限の定めがない場合でも、保存行為(修理など)はOK | 「権限ないと何もできない」と思いがち。➡️保存行為は例外 |
| 自己契約・双方代理は禁止(原則) | 「本人に有利ならOK」と思いがち。➡️本人の承諾がなければNG |
| 代理人に行為能力(未成年など)がなくても代理は有効 | 「未成年が代理人は無効」と思いがち。➡️OK |
| **代理権の濫用(自分の利益目的など)**は原則有効。ただし、相手方が悪意・有過失なら無効。 | 「濫用なら常に無効」と思いがち。➡️相手方の認識がポイント |
🔍具体例での引っかけパターン
❌【ひっかけ1】
無権代理でも、相手方が善意・無過失なら有効になる。
→ ❌誤り。本人が追認しない限り、無権代理は無効。
❌【ひっかけ2】
代理人に制限行為能力(例:未成年)があると代理行為は無効。
→ ❌誤り。代理人自身の行為能力は不要。
❌【ひっかけ3】
双方代理は常に有効である。
→ ❌誤り。本人の承諾がなければ無効。
❌【ひっかけ4】
代理人が本人のためと言って自己に売却した契約は有効。
→ ❌誤り。自己契約は原則禁止(本人の承諾が必要)。
📝合格のコツ:代理は「誰の名前で、誰に効力が帰属するか」に注目!
- 【代理】→ 他人の名義で行動 → 本人に効果が帰属
- 【使者】→ メッセンジャー(自分の意思は関与しない)
- 【無権代理】→ 無効(ただし追認で有効化)
- 【制限能力者の代理】→ OK(行為能力は関係ない)
📚最後に一言:
「代理」は民法の中でも混乱しやすく、毎年出題される重要テーマ免責的債務引き受けとは何か 宅建試験対策 民法 権利関係 債権譲渡
The following two tabs change content below.

Mai
投資家・宅地建物取引士
不動産投資、株式投資、自由で豊かに生きるマインドについての情報を発信
前職は外資IT
神戸市 東灘区生まれ 関西大学 法学部 卒業
最新記事 by Mai (全て見る)
- 脱出おひとり島5の感想 ネトフリ 韓国イケメンについて/솔로지옥5 - 08/02/2026
- 芦屋 ホテル竹園芦屋 ディナー すき焼き&ステーキが美味しい - 07/02/2026
- 衆院選2026 兵庫県 期日前投票にいってきました 選挙の価値は450万円以上 - 07/02/2026
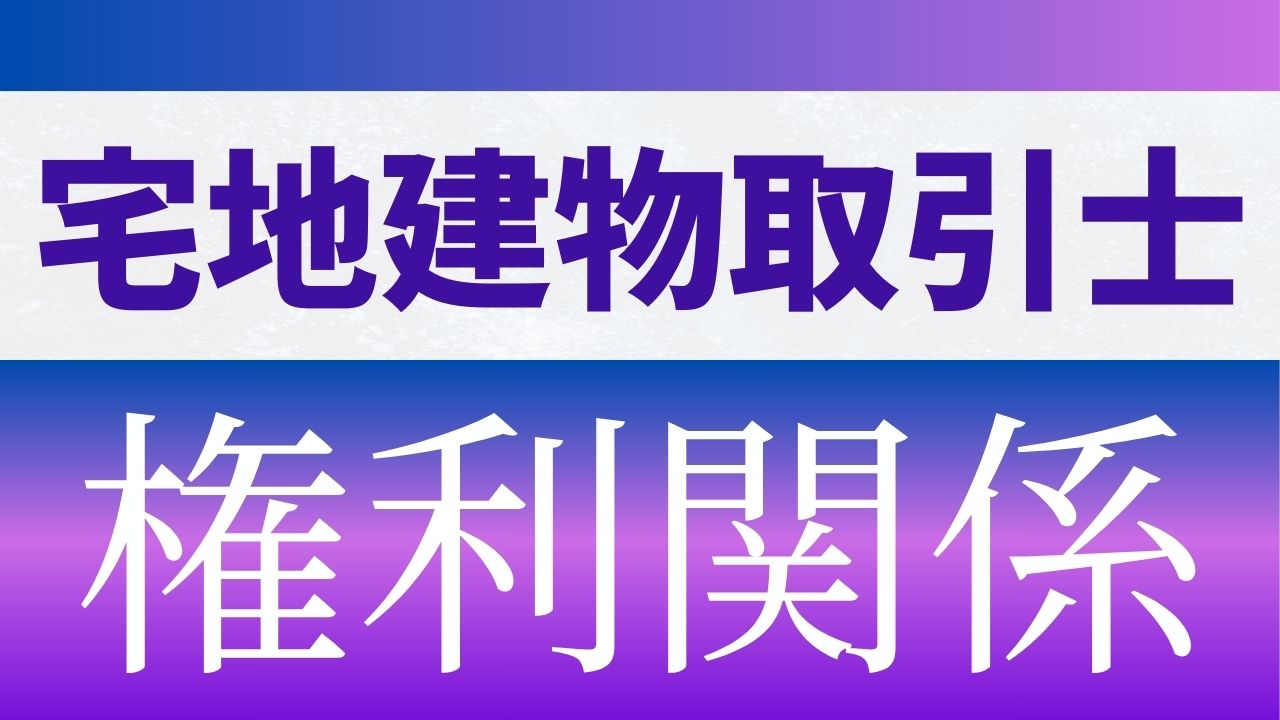
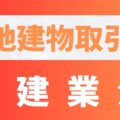

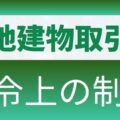
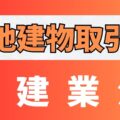


コメント