🔹基本の流れ
債務者 → 受益者(最初にもらった人)
受益者 → 転得者(さらにもらった人)
🔹原則
取消の相手は「受益者」または「転得者」。
ただし、効力が及ぶかは「善意・悪意」で変わる。
🔹ケースごとの整理
① 受益者が悪意(=害を与えると知ってた)
→ 債権者は当然に取消請求できる。
その後の転得者も悪意なら効力は及ぶ。
② 受益者が善意(=害を知らなかった)
→ この時点で取消できない。
なぜなら「善意の受益者を害するのはかわいそう」って考え方やね。
👉 つまり、受益者が善意の場合、たとえ転得者が悪意でも取消できない。
🔹条文の根拠
民法424条の6第2項
「受益者が善意であった場合は、転得者が悪意であっても取消しをすることはできない。」権利関係
The following two tabs change content below.

Mai
投資家・宅地建物取引士
不動産投資、株式投資、自由で豊かに生きるマインドについての情報を発信
前職は外資IT
神戸市 東灘区生まれ 関西大学 法学部 卒業
最新記事 by Mai (全て見る)
- 2025年の100の感謝 ノートに書くワーク /ロンダ・バーン - 15/02/2026
- 第4講 SNS運用 /SNS Marketing,Business - 12/02/2026
- 私は絶対シリウス星人だと気づいた本日。 スピリチュアルな話 - 12/02/2026
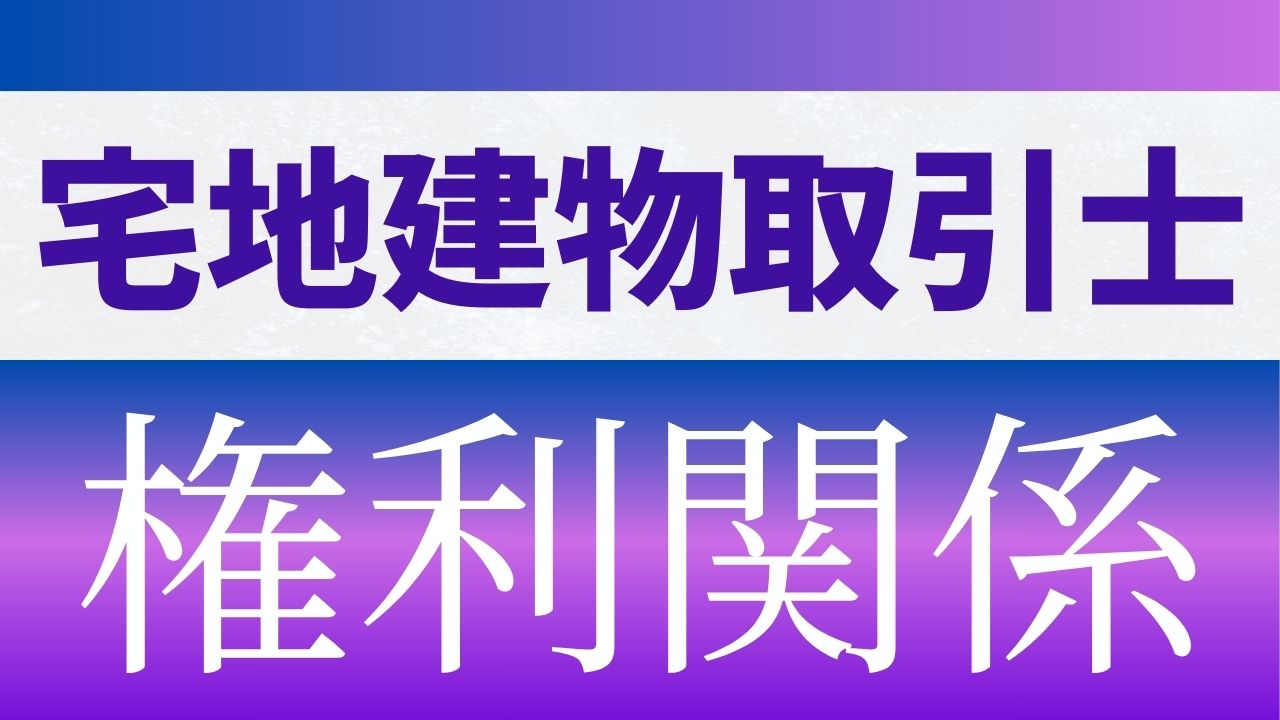
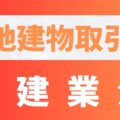
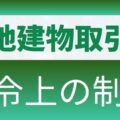
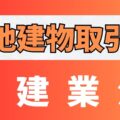



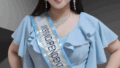
コメント